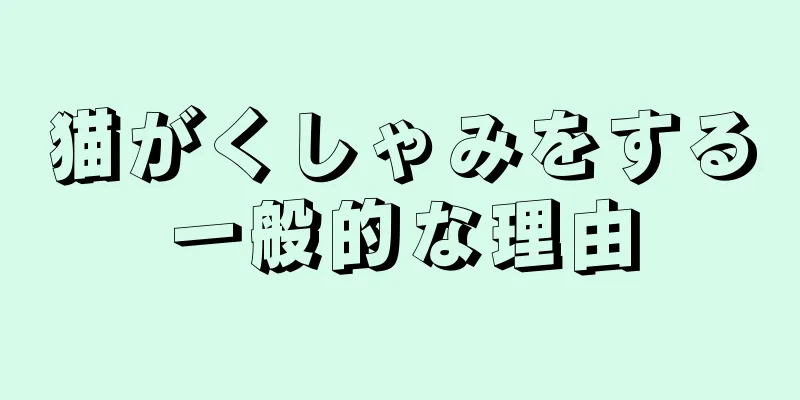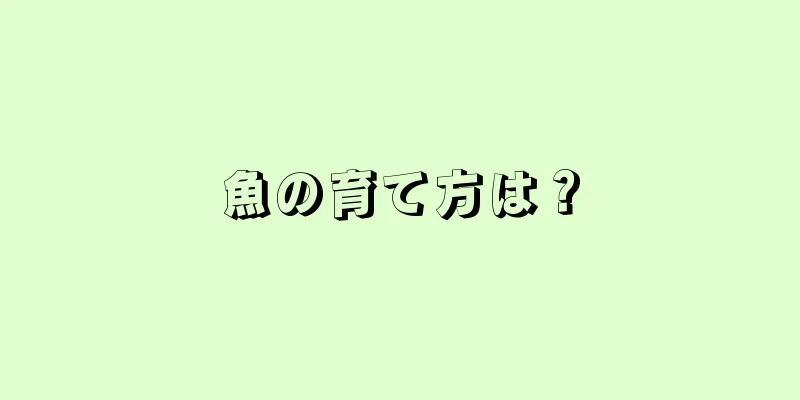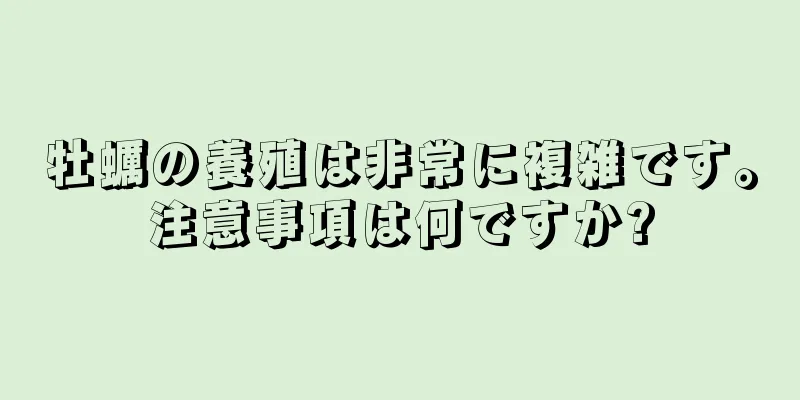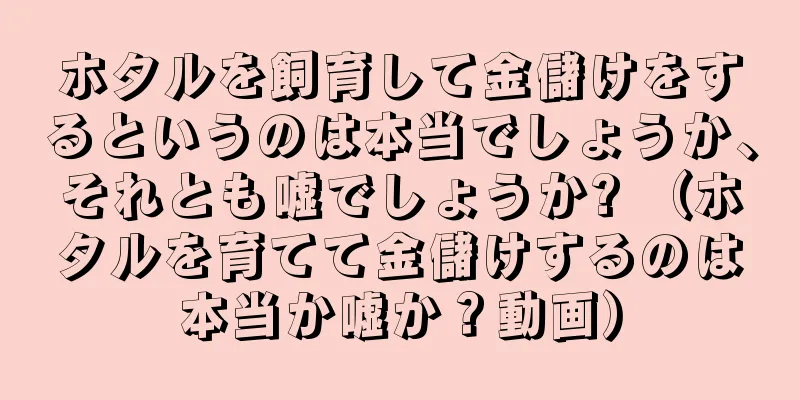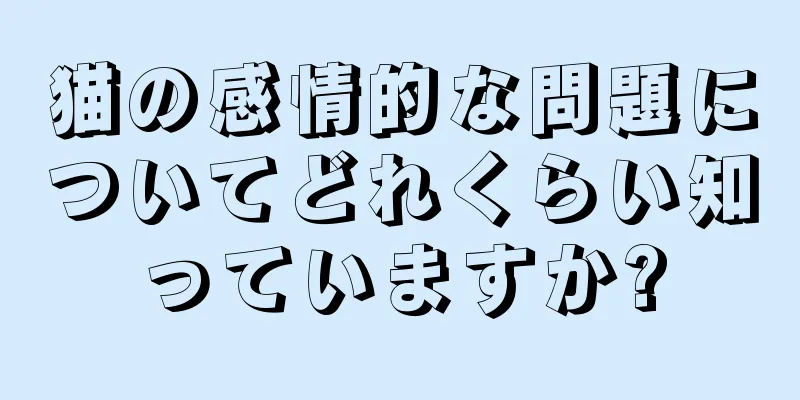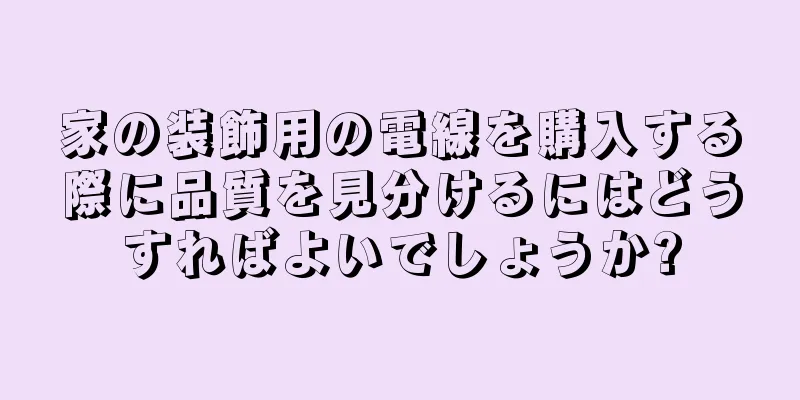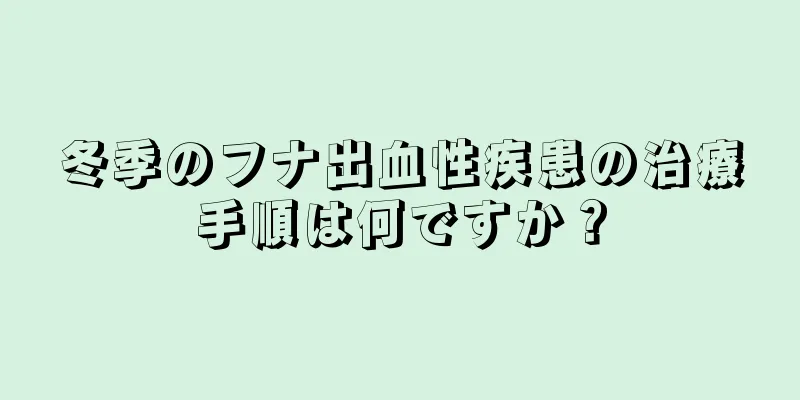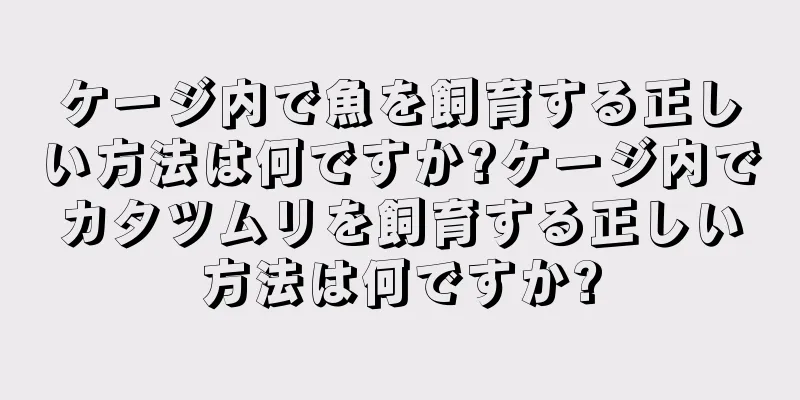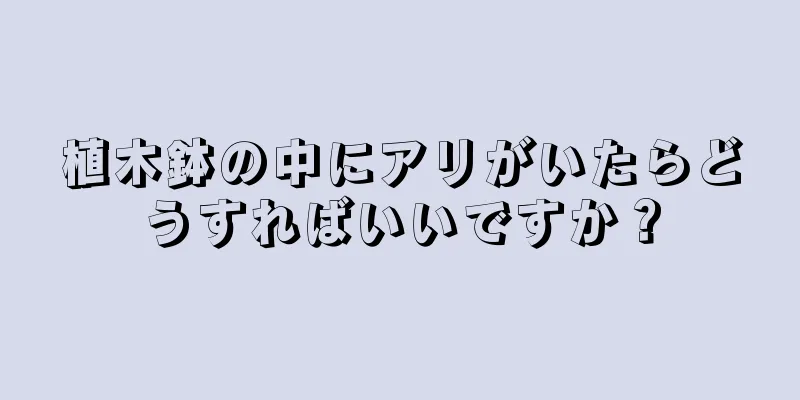エビ養殖技術と方法、エビとグリーンシュリンプの違い
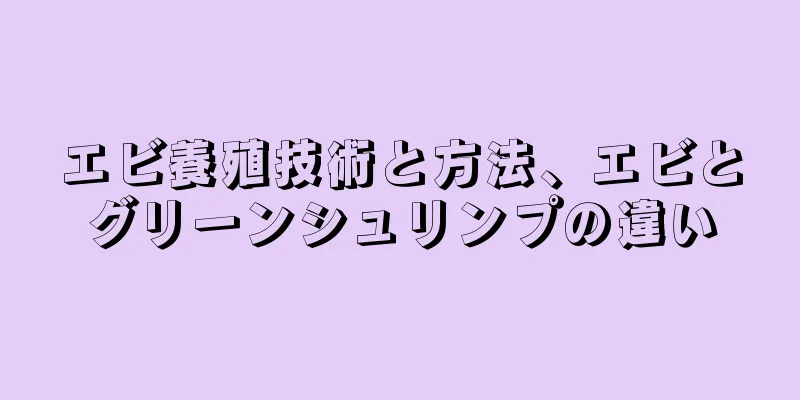
|
1. 池の要件:白エビの養殖を例にとると、池の深さは一般的に約1.8mです。池には完全な給排水システムが必要であり、池の周囲には十分な水が供給され、飼育水中の栄養素は白エビの栄養ニーズを満たすことができなければなりません。 2. 温室構造:温室構造は一般的に「人」の字型をしており、建設の難易度を軽減できるだけでなく、建設資材も節約できます。 3. 殺菌:稚エビを放流する前に、池を殺菌する必要があります。通常、稚エビを正式に放流する 25 日前に、消毒のために生石灰を池に追加することができます。 1. エビ養殖技術 1. 池の要件 (1)白エビの養殖を例にとると、池の深さは1.8m程度必要となる。 (2)池には完全な給排水設備が備えられており、その周囲には十分な水資源がなければならない。さらに、養殖水中の栄養素は白エビの栄養ニーズを満たす必要があります。 (3)池内には、一定時間内に酸素が供給され、十分な溶存酸素が確保されるよう、定出力酸素供給装置を設置すること。 2. 温室フレーム (1)温室構造は主に人型をしており、建設の難易度を軽減し、建設資材を節約できる。 (2)温室は竹木フレーム構造を採用しており、解体や除塵に便利であり、竹木フレームもリサイクル可能である。 (3)被覆フィルムの厚さは0.6~0.8mmとし、光透過率が良好であることが必要である。フィルムの色はできるだけ白にしてください。 3. 殺菌 (1)稚エビを放流する前には、殺菌処理を行わなければならない。稚エビの正式放流の約 25 日前に、消毒のために生石灰を池に追加することができます。 (2)生石灰消毒後、必ず1週間前に適切な濃度のカルキを池に投入してください。鶏糞などの肥料を適量加えても良いでしょう。 4. エビの種苗管理 (1)エビフライを選ぶ ①温室でオショロコマエビを飼育する場合、池の水は一般的に淡水なので、脱塩したエビの品種を選ぶことが重要です。 ②また、温室池の養殖条件に応じて、温室池環境に適応できるエビ種を選定し、市場での販売実績が高いエビ種苗を選択するよう努める必要がある。 (2)非毒性試験を実施する エビの稚魚を選別した後、無毒性試験を実施する必要があります。これにより、エビの稚魚のすべての指標が指定された要件を満たしていることが保証され、エビの稚魚間でのウイルスの伝染を防ぐことができます。 (3)物事を野放しにする ① 放流前には必ず稚エビの入った袋を池の中に15分ほど置いておき、袋の中の稚エビが池の水温や基本環境に順応できるようにします。 ② 順応したら袋を外し、数匹ずつ池に放します。これにより、稚エビのストレス反応を軽減し、環境に適応できないためにエビが大量に死ぬのを防ぐことができます。 ③放流する稚エビの数は池の大きさに合わせてください。一般的には、池に固定グリッドを設置し、各グリッドに一定数のエビの稚魚を放流することで、エビの稚魚が泳ぎ回らないようにします。 5. 給餌と管理 (1)エビの成長状況に応じて適切な餌を与え、エビの成長ニーズを満たす量の餌を与える。食べ過ぎないでください。食べ過ぎると無駄になります。餌を少なすぎると成長にも影響が出るので注意してください。 (2)餌の無駄を避け、過剰な餌が池の水質に与える影響を減らすために、エビの食習慣に合った餌を与える時間が必要です。 6. 水質を規制する (1)水質の変化に応じて適時に水質を調整する必要がある。池の水質の変化を一定の頻度で監視し、水質の変化をタイムリーに把握することができます。そして、餌の量を減らすことで池の水質を効果的に調整することができます。 (2)季節に応じて水温を適宜調節できる。水温が変化する場合には、水温の変動がエビの成長に影響を与えないように、水温を安定させるための適切な措置を講じる必要があります。 7. 水中の溶存酸素量を調整する (1)水中の溶存酸素量に応じて、適時に溶存酸素量を適切なレベルに調整することができる。 (2)一般的には、プール内の酸素ポンプを通じて池の水に酸素を注入し、溶存酸素量検出装置を通じて水中の溶存酸素量を検出し、基準を満たしているかどうかを確認することができる。溶存酸素量が基準に達すると、酸素の供給を停止できます。 (3)水中の溶存酸素量は季節によって異なるため、溶存酸素量を柔軟に調整する必要があることに留意する。 8. 疾病予防と管理 (1)一般的に、温室池で一定期間飼育すると、池の中に多量の泥や細菌が蓄積します。沈泥やバクテリアが時間内に除去されない場合、池の水質が悪化するだけでなく、病気も発生します。したがって、水質を改善し、病気の可能性を減らすために、池を適時に清掃する必要があります。 (2)グリッド飼育は、ウイルスを効果的に隔離し、エビ間の伝染を防ぎ、病気の発生地域を減らすために使用することができます。 (3)稚エビの成長状況から、稚エビが感染している病気の種類を判断し、適切な治療法を処方することで、稚エビの病気の予防と制御の質を向上させることができる。 2. エビと海老の違い 1. エビの体の色は青緑色で、茶緑色の縞模様があります。頭胸部と腹部の境界は非常に明瞭です。頭胸部は比較的厚く、腹部から徐々に小さくなります。体は20の節から構成されています。メスのチャイニーズエビの体色は一般的に灰緑色ですが、オスのエビの体色は黄色です。全部で21の節から成り、前節と最終節を除く各節には一対の付属肢がある。 2. 白エビを飼育する場合、淡水で飼育する場合は、淡水の pH 値が 6.5 ~ 8.5 である必要があります。海水で飼育する場合は、海水の pH 値が 7 ~ 8.5 である必要があります。稚魚を放流する際、水温は20℃未満にはならず、33℃を超えてはいけません。水温が20℃以下の場合は、冬小屋を建てたり、白砂を敷いたり、水位を深くしたりすることで水温を上げることができます。水温が33℃を超える場合は、水位を深くしたり、エアレーション装置を増やしたりすることで水温を下げることができます。 3. エビ養殖の過程では、水質を清潔に保つために定期的に水を交換する必要があります。水中の溶存酸素量が不十分な場合は、エビの成長に十分な酸素が供給されるように、酸素供給装置を適時に作動させる必要があります。また、水の透明度とpHを制御し、pH値の変化を減らし、エビの成長に影響を与える可能性のあるpH値の過度な変化を避ける必要があります。 |
>>: 鯉の鰓蓋が開いていますが、虫はいますか?どのように治療すればいいですか?
推薦する
飼料販売のヒント: 効率的な飼料ビジネスを運営する方法
畜産の急速な発展に伴い、飼料販売は大きな可能性を秘めた産業となりました。飼料販売員として、競争の激し...
放し飼いの鶏のメリットトップ10:放し飼いの鶏を適切に育てる方法
導入放し飼いの鶏とは、開放された環境で自由に動き回り、餌を食べることが許されている鶏のことです。伝統...
魚不均衡症候群の赤フナを治療するには?
魚不均衡症候群の赤フナを治療するには?魚のバランスが崩れる原因は、先天的なメカニズムの障害や後天的な...
ハエは何を食べますか? (ハエは生き残るために何を食べるのか)
1. ハエは普段何を食べるのが好きですか?ハエは甘いものや死肉を食べるのが好きで、アブラムシバエや...
広西八尾飼料株式会社のプロフィール、製品、品質は何ですか?
広西八尾飼料株式会社の概要広西八尾飼料有限公司は2005年に設立され、飼料の生産と販売を専門とする企...
カタツムリの飼育について知っておくべき小さなことは何ですか? (カタツムリの飼育について知っておくべき小さなことは何ですか?)
1. カタツムリに餌を与えるには?まず、カタツムリを飼育するには、保湿性に優れた木箱を使うのが最適...
副業として自宅で飼育するのに適した観賞魚はどれでしょうか?
副業として自宅で飼育するのに適した観賞魚はどれでしょうか?それらは副業としては適していません。うまく...
最新の赤虫養殖場建設基準(赤虫養殖場建設基準の最新版)
1. 赤虫を育てるには苗が必要ですか?赤いミミズを栽培するには、苗を植える必要があります赤虫を飼育...
フグの飼育方法を教えてください。
1. フグの飼育方法を教えてください。潜水艦には海水が必要だと誰が言ったのですか? ! 〜追加しな...
肝臓がんは治りますか?
転移が起こっているとのことですが、これは中期または後期段階であるはずです。進行した転移性肝臓がんを放...
カイコを上手に育てるにはどうすればいいですか? (カイコを上手に育てる方法)
1. カイコの飼育方法は? 1. 桑の葉を摘みます。桑の葉は蚕の餌になります。餌を与えるときは、新...
Koiアプリは1日にどれくらい稼げますか
1. Koiアプリは1日にどれくらい稼げるか50 から 100。Koi はエリート向けに設計されたソ...
カニ養殖技術と方法、水質の要件は何ですか
1. カニ養殖技術と方法、水質の要件は何ですか1. 池を作る:適切な大きさの池を作ります。池の高さは...
スッポン、丸い魚、リクガメは同じ動物ですか?
スッポン、丸い魚、リクガメは同じ動物ですか?カメ(スッポン、水魚とも呼ばれ、一般にはカメとして知られ...
フナの養殖にかかる費用と利益はおおよそいくらですか?
フナは私の国で最も一般的な淡水魚の一つで、主な地域以外の水系に生息していることが多いです。フナは食性...